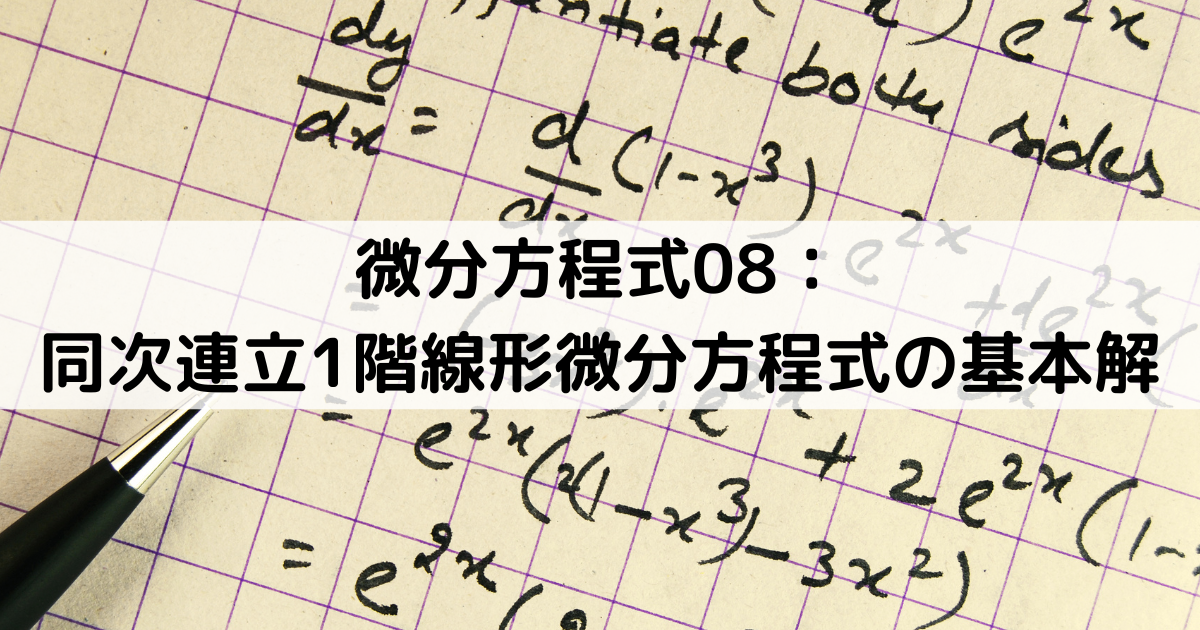こんにちは、ひかりです。
今回は微分方程式から同次連立1階線形微分方程式の基本解について解説していきます。
この記事では以下のことを紹介します。
- 連立1階線形微分方程式の解の存在と一意性について
- 同次連立1階線形微分方程式の基本解について
- ロンスキアンとリウビィルの公式について
連立1階線形微分方程式の解の存在と一意性
今回から数回の記事では、応用上よく用いられる線形微分方程式について見ていきます。
まずは一般的な線形微分方程式に対してどこまで解の表示ができるかを見ていきます。
そのため、次の連立1階微分方程式
$$ y’_i(x)=\sum_{j=1}^na_{ij}(x)y_j(x)+b_i(x), \quad (i=1,2,\cdots,n) $$
の解の存在と一意性を示しましょう。
ここで、 \( y_i(x) \) は未知関数、 \( a_{ij}(x),b_i(x) \) は既知関数になります。
このとき、
$$ \mathbf{y}(x)=\begin{pmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix}, \quad A(x)=\begin{pmatrix} a_{11}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & \cdots & a_{nn}(x) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}(x)=\begin{pmatrix} b_1(x) \\ \vdots \\ b_n(x) \end{pmatrix} $$
とおくと、この方程式は次のように表せます。
$$ \mathbf{y}'(x)=A(x)\mathbf{y}(x)+\mathbf{b}(x) $$
この方程式は
$$ \{ \mathbf{y}(x) \ | \ \mathbf{y}'(x)=A(x)\mathbf{y}(x)+\mathbf{b}(x) \} $$
が線形空間(ベクトル空間)になることから、連立1階線形微分方程式といいます。
さらに、 \( \mathbf{b}(x) \equiv 0 \) のとき、この方程式を同次連立1階線形微分方程式といい、 \( \mathbf{b}(x) \not\equiv 0 \) のとき、この方程式を非同次連立1階線形微分方程式といいます。
それでは、微分方程式07の定理5を用いて、連立1階線形微分方程式の解の存在と一意性を示しましょう。
\( x_0\in \mathbb{R}, \ r>0 \) とする。このとき、 \( A(x),\mathbf{b}(x) \) を
$$ E=\{ x \ | \ |x-x_0|≦r \} \ (\subset \mathbb{R}) $$
上連続とすると、連立1階線形微分方程式の初期値問題
$$ \begin{cases} \mathbf{y}'(x)=A(x)\mathbf{y}(x)+\mathbf{b}(x) \\ \mathbf{y}(x_0)=\mathbf{y}_0 \end{cases} $$
の解が \( x=x_0 \) の近傍でただ一つ存在する。
定理1の証明(気になる方だけクリックしてください)
\( A(x),\mathbf{b}(x) \) が \( E \) 上連続であるので、 \( A(x),\mathbf{b}(x) \) は
$$ E=\{ x \ | \ |x-x_0|≦r \} \ (\subset \mathbb{R}) $$
上有界となります。よって、
$$ \sup_{x\in E}|a_{ij}(x)|+\sup_{x\in E}|b_i(x)|≦K<\infty \quad (i,j=1,2,\cdots,n) $$
とおきます。すると、シュワルツの不等式より、
$$ \begin{align} \|A(x)\mathbf{y}(x)\|^2&=\sum_{i=1}^n\left| \sum_{j=1}^na_{ij}(x)y_j\right|^2≦\sum_{i=1}^n\left( \sum_{j=1}^nK|y_j|\right)^2 \\ &≦\sum_{i=1}^n\left( \sum_{j=1}^nK^2\right)\left( \sum_{j=1}^n|y_j|^2\right)=n^2K^2\|\mathbf{y}(x)\|^2 \end{align} $$
したがって、
$$ \|A(x)\mathbf{y}(x)\|≦nK\|\mathbf{y}(x)\| $$
ここで、
$$ D=\{ (x,\mathbf{y}) \ | \ |x-x_0|≦r, \ \|\mathbf{y}-\mathbf{y}_0\|≦\rho \} $$
$$ \mathbf{f}(x,\mathbf{y})=A(x)\mathbf{y}(x)+\mathbf{b}(x) $$
とおきます。すると、 \( (x,\mathbf{y})\in D \) のとき、
$$ \begin{align} \|\mathbf{f}(x,\mathbf{y})\|&=\|A(x)\mathbf{y}(x)+\mathbf{b}(x)\| \\ &=\|A(x)(\mathbf{y}-\mathbf{y}_0)+A(x)\mathbf{y}_0+\mathbf{b}(x)\| \\ &≦\|A(x)(\mathbf{y}-\mathbf{y}_0)\|+\|A(x)\mathbf{y}_0\|+\|\mathbf{b}(x)\| \\ &≦nK\rho+nK\|\mathbf{y}_0\|+\sqrt{n}K \end{align} $$
また、 \( (x,\mathbf{y}),(x,\mathbf{z})\in D \) に対して、
$$ \begin{align} &\|\mathbf{f}(x,\mathbf{y})-\mathbf{f}(x,\mathbf{z})\| \\ &=\|A(x)\mathbf{y}+\mathbf{b}(x)-(A(x)\mathbf{z}+\mathbf{b}(x))\| \\ &=\|A(x)(\mathbf{y}-\mathbf{z})\|≦nK\|\mathbf{y}-\mathbf{z}\| \end{align} $$
したがって、
$$ M=nK\rho+nK\|\mathbf{y}_0\|+\sqrt{n}K, \quad L=nK $$
とおくと、
$$ \begin{cases} \| \mathbf{f}(x,\mathbf{y})\|≦M \\ \|\mathbf{f}(x,\mathbf{y})-\mathbf{f}(x,\mathbf{z})\|≦L\|\mathbf{y}-\mathbf{z}\| \end{cases} $$
さらに、 \( A(x),\mathbf{b}(x) \) が \( E \) 上連続であるので、 \( \mathbf{f}(x,\mathbf{y}) \) の連続性もわかります。
よって、微分方程式07の定理5より、解の存在と一意性がいえます。
同次連立1階線形微分方程式の基本解
解の存在と一意性がいえたので、実際に解を求めていきましょう。
まずは、同次連立1階線形微分方程式の初期値問題
$$ \begin{cases} \mathbf{y}'(x)=A(x)\mathbf{y}(x) \\ \mathbf{y}(x_0)=\mathbf{y}_0\in \mathbb{C}^n \end{cases} \tag{1} $$
を考えます。
はじめに、 \( \mathbb{C}^n \) の基底を \( \{ \mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\} \) とすると、初期値 \( \mathbf{y}_0 \) は
$$ \mathbf{y}_0=\alpha_1\mathbf{v}_1+\cdots+\alpha_n\mathbf{v}_n \quad (\alpha_i\in \mathbb{C}) $$
と表されます。
このとき、 \( \mathbf{y}_k(x) \) を
$$ \begin{cases} \mathbf{y}’_k(x)=A(x)\mathbf{y}_k(x) \\ \mathbf{y}_k(x_0)=\mathbf{v}_k \end{cases} \tag{2} $$
の解とします。(\( \mathbf{y}_k \) の存在と一意性は定理1からいえます)
そして、
$$ \mathbf{y}(x)=\sum_{k=1}^n\alpha_k\mathbf{y}_k(x) $$
とおくと、これが方程式(1)の解となります。実際、
$$ \begin{align} \mathbf{y}'(x)&=\left( \sum_{k=1}^n\alpha_k\mathbf{y}_k(x) \right)’=\sum_{k=1}^n\alpha_k\mathbf{y}’_k(x)=\sum_{k=1}^n\alpha_kA(x)\mathbf{y}_k(x) \\ &=A(x)\left( \sum_{k=1}^n\alpha_k\mathbf{y}_k(x) \right) =A(x)\mathbf{y}(x) \end{align} $$
$$ \begin{align} \mathbf{y}(x_0)&=\sum_{k=1}^n\alpha_k\mathbf{y}_k(x_0)=\sum_{k=1}^n\alpha_k\mathbf{v}_k=\mathbf{y}_0 \end{align} $$
したがって、
$$ \mathbf{y}(x)=\sum_{k=1}^n\alpha_k\mathbf{y}_k(x) \tag{3} $$
が方程式(1)の解となり、定理1よりこれ以外の解は存在しません。
そこで、
$$ Y(x)=\begin{pmatrix} \mathbf{y}_1(x) & \mathbf{y}_2(x) & \cdots & \mathbf{y}_n(x) \end{pmatrix} : \ n\times n 型行列値関数 $$
$$ V=\begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{pmatrix} : \ n次正則行列 $$
(\( \{ \mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\} \)が \( \mathbb{C}^n \) の基底であるので、線形代数学続論06の定理6から \( V \) は正則行列となります。)
とおきます。すると、方程式(2)は
$$ \begin{cases} Y'(x)=A(x)Y(x) \\ Y(x_0)=V \end{cases} \tag{4} $$
と表すことができて、微分方程式06の定理1より、これは積分方程式
$$ Y(x)=V+\int_{x_0}^xA(\xi)Y(\xi)d\xi $$
を解けばよいことになります。これをピカールの逐次近似法を用いて解いていきます。
$$ \begin{cases} Y_0(x)=V \\ \displaystyle Y_m(x)=V+\int_{x_0}^xA(\xi)Y_{m-1}(\xi)d\xi \quad (m=1,2,\cdots) \end{cases} $$
とおくと、
$$ Y_1(x)=V+\int_{x_0}^xA(\xi_1)Y_0(\xi_1)d\xi_1=\left( E+\int_{x_0}^xA(\xi_1)d\xi_1 \right)V \quad (積の順序に注意) $$
$$ \begin{align} Y_2(x)&=V+\int_{x_0}^xA(\xi_1)Y_1(\xi_1)d\xi_1 \\ &=V+\int_{x_0}^xA(\xi_1)\left(E+\int_{x_0}^{\xi_1}A(\xi_2)d\xi_2 \right)Vd\xi_1 \\ &=\left( E+\int_{x_0}^xA(\xi_1)d\xi_1+\int_{x_0}^x\int_{x_0}^{\xi_1}A(\xi_1)A(\xi_2)d\xi_2d\xi_1 \right) V \end{align} $$
となり、以下帰納的に
$$ Y_m(x)=\left( E+\sum_{k=1}^m\int_{x_0}^x\int_{x_0}^{\xi_1}\cdots\int_{x_0}^{\xi_{k-1}}A(\xi_1)A(\xi_2)\cdots A(\xi_k)d\xi_k\cdots d\xi_2d\xi_1 \right) V $$
となるため、 \( m\to \infty \) での極限をとると、
$$ Y(x)=\left( E+\sum_{k=1}^{\infty}\int_{x_0}^x\int_{x_0}^{\xi_1}\cdots\int_{x_0}^{\xi_{k-1}}A(\xi_1)A(\xi_2)\cdots A(\xi_k)d\xi_k\cdots d\xi_2d\xi_1 \right) V $$
となります。
( \( A(\xi_1)A(\xi_2)\cdots A(\xi_k) \) は行列の積なので交換できないことに注意してください。)
この \( Y(x) \) の式のことをペアノ・ベーカー級数といいます。さらに、
$$ \mathbf{y}_0=\sum_{k=1}^n\alpha_k\mathbf{v}_k \quad (\alpha_k\in \mathbb{C}), \quad \mathbf{\alpha}=\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}\in \mathbb{C}^n $$
とおくと、
$$ \mathbf{y}_0=\begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}=V\mathbf{\alpha} $$
\( V \) は正則行列であるので、
$$ \mathbf{\alpha}=V^{-1}\mathbf{y}_0=Y(x_0)^{-1}\mathbf{y}_0 \quad (方程式(4)の初期値より) \tag{5} $$
したがって、式(5)と式(3)から、方程式(1)の解は次のように表されます。
$$ \begin{align} \mathbf{y}(x)&=\sum_{k=1}^n\alpha_k\mathbf{y}_k(x)=\begin{pmatrix} \mathbf{y}_1(x) & \cdots & \mathbf{y}_n(x) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \\ &=Y(x)\mathbf{\alpha}=Y(x)Y(x_0)^{-1}\mathbf{y}_0 \end{align} $$
\( Y(x),Y(x_0)^{-1} \) は基底のとり方に依存しますが、その積 \( Y(x)Y(x_0)^{-1} \) は方程式(1)の解の一意性から基底のとり方に依存しないことに注意してください。
この \( Y(x)Y(x_0)^{-1} \) を \( R(x,x_0) \) と表して、レゾルベントといいます。
まとめると、
方程式(2)の解 \( \{\mathbf{y}_1(x),\mathbf{y}_2(x),\cdots,\mathbf{y}_n(x) \} \) を同次連立1階線形微分方程式(1)の基本解という。
(これは基底のとり方に依存する。また、一次独立である。)
また、
$$ Y(x)=\begin{pmatrix} \mathbf{y}_1(x) & \mathbf{y}_2(x) & \cdots & \mathbf{y}_n(x) \end{pmatrix} $$
とおくとき、 \( Y(x)Y(x_0)^{-1} \) をレゾルベントといい、 \( R(x,x_0) \) と表す。
同次連立1階線形微分方程式
$$ \begin{cases} \mathbf{y}'(x)=A(x)\mathbf{y}(x) \\ \mathbf{y}(x_0)=\mathbf{y}_0\in \mathbb{C}^n \end{cases} $$
の解 \( \mathbf{y}(x) \) はレゾルベントを用いて、次のように表される。
$$ \mathbf{y}(x)=R(x,x_0)\mathbf{y}_0=Y(x)Y(x_0)^{-1}\mathbf{y}_0 $$
ロンスキアンとリウビィルの公式
次に、同次連立1階線形微分方程式の一般解(つまり、初期値を指定しない解)を求めてみましょう。
そのために、次のロンスキアンというものを定義します。
\( n \) 個の \( n \) 次元ベクトル値関数 \( \mathbf{y}_1(x),\cdots,\mathbf{y}_n(x) \) (方程式の解でなくてもよい)に対して、行列式
$$ \det \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1(x) & \cdots & \mathbf{y}_n(x) \end{pmatrix} $$
を \( \mathbf{y}_1(x),\cdots,\mathbf{y}_n(x) \) のロンスキアンといい、
$$ W(\mathbf{y}_1,\cdots,\mathbf{y}_n)(x), \quad W(\mathbf{y}_1(x),\cdots,\mathbf{y}_n(x)) $$
などと表す。このシリーズでは単に \( W(x) \) と表す。
また、行列のトレースを定義しましょう。
\( n \) 次正方行列
$$ A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} $$
に対して、 \( A \) のトレース \( \text{tr}A \) を次で定義する。
$$ \text{tr}A=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn} $$
このとき、同次連立1階線形微分方程式とロンスキアンの間には次の公式が成り立ちます。
\( \mathbf{y}_k(x) \ (k=1,2,\cdots,n) \) がそれぞれ同次連立1階線形微分方程式
$$ \mathbf{y}’_k(x)=A(x)\mathbf{y}_k(x) $$
をみたすとすると、そのロンスキアン \( W(x) \) は次のように表される。
$$ W(x)=W(x_0)\exp \left( -\int_{x_0}^x\text{tr}A(\xi)d\xi \right) $$
とくに、 \( \displaystyle \exp \left( -\int_{x_0}^x\text{tr}A(\xi)d\xi \right) \not=0 \) であるので、
$$ W(x_0)\not=0 \ \iff \ 任意のxに対して、 W(x)\not=0 $$
定理3の証明(気になる方だけクリックしてください)
行列式の性質を用いることにより、次を示せば定理3が成り立ちます。
$$ W'(x)=(\text{tr}A(x))W(x) \tag{6} $$
なぜなら、式(6)が成り立つとすると、これは \( W \) に関する1階線形微分方程式であるので、定数変化公式を用いることにより、
$$ W(x)=W(x_0)\exp \left( -\int_{x_0}^x\text{tr}A(\xi)d\xi \right) $$
となるからです。それでは、式(6)を示していきましょう。
話を簡単にするために \( n=2 \) の場合で示します。(一般の \( n \) でも同様)
$$ \mathbf{y}_1(x)=\begin{pmatrix} y_{11}(x) \\ y_{21}(x) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y}_2(x)=\begin{pmatrix} y_{12}(x) \\ y_{22}(x) \end{pmatrix} $$
とすると、行列式の定義より、
$$ \begin{align} W'(x)&=\frac{d}{dx}\begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) \end{vmatrix} \\ &=\frac{d}{dx} \left( \sum_{\sigma\in S_2}\text{sgn}(\sigma)y_{1\sigma(1)}(x)y_{2\sigma(2)}(x) \right) \\ &=\sum_{\sigma\in S_2}\text{sgn}(\sigma)\frac{dy_{1\sigma(1)}(x)}{dx}y_{2\sigma(2)}(x)+\sum_{\sigma\in S_2}\text{sgn}(\sigma)y_{1\sigma(1)}(x)\frac{dy_{2\sigma(2)}(x)}{dx} \\ &=\begin{vmatrix} y’_{11}(x) & y’_{12}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) \\ y’_{21}(x) & y’_{22}(x) \end{vmatrix} \end{align} $$
ここで、 \( \mathbf{y}’_1=A\mathbf{y} \) であるので、行列式の性質により、
$$ \begin{align} \begin{vmatrix} y’_{11}(x) & y’_{12}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) \end{vmatrix}&=\begin{vmatrix} a_{11}y_{11}+a_{12}y_{21} & a_{11}y_{12}+a_{12}y_{22} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} \\ &=\begin{vmatrix} a_{11}y_{11} & a_{11}y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{12}y_{21} & a_{12}y_{22} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} \\ &=a_{11}\begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}+0 \\ &=a_{11}W(x) \end{align} $$
同様に、
$$ \begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) \\ y’_{21}(x) & y’_{22}(x) \end{vmatrix}=a_{22}W(x) $$
が示せるので、
$$ W'(x)=(a_{11}+a_{22})W(x)=(\text{tr}A(x))W(x) $$
よって、定理3が成り立ちます。
方程式(1)の基本解 \( Y(x)=\begin{pmatrix} \mathbf{y}_1(x) & \cdots & \mathbf{y}_n(x) \end{pmatrix} \) は一次独立であるので、基本解の初期値でのロンスキアンは、
$$ W(x_0)=\det \begin{pmatrix} \mathbf{y}_1(x_0) & \cdots & \mathbf{y}_n(x_0) \end{pmatrix}\not=0 $$
であるので、定理3より、
$$ Y(x):基本解 \ \Rightarrow \ W(x_0)\not=0 \ \Rightarrow \ 任意のxに対して、W(x)\not=0 $$
したがって、同次連立1階線形微分方程式
$$ \mathbf{y}'(x)=A(x)\mathbf{y}(x) $$
の一般解は次のように与えられます。
方程式(1)の基本解を
$$ Y(x)=\begin{pmatrix} \mathbf{y}_1(x) & \cdots & \mathbf{y}_n(x) \end{pmatrix} $$
とするとき、同次連立1階線形微分方程式
$$ \mathbf{y}'(x)=A(x)\mathbf{y}(x) $$
の一般解は次で表される。
$$ \mathbf{y}(x)=C_1\mathbf{y}_1(x)+\cdots+C_n\mathbf{y}_n(x), \quad (C_1,\cdots,C_n:任意定数) $$
定理4の証明(気になる方だけクリックしてください)
\( n=2 \) で示します。(一般の \( n \) でも同様)
このとき、方程式(1)の基本解
$$ Y(x)=\begin{pmatrix} \mathbf{y}_1(x) & \mathbf{y}_2(x) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) \end{pmatrix} $$
は上の考察より、任意の \( x \) に対して、
$$ W(x)=\begin{vmatrix} y_{11}(x) & y_{12}(x) \\ y_{21}(x) & y_{22}(x) \end{vmatrix}\not=0 $$
となります。よって、基本解の初期値 \( x_0 \) に対して、連立一次方程式
$$ \begin{cases} y_{11}(x_0)\xi_1+y_{12}(x_0)\xi_2=y_1(x_0) \\ y_{21}(x_0)\xi_1+y_{22}(x_0)\xi_2=y_2(x_0) \end{cases} \quad \left( ここで、\mathbf{y}(x)=\begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} \right) $$
はただ一組の解 \( \xi_1=C_1, \xi_2=C_2 \) をもちます。
(この連立一次方程式は定数係数の連立一次方程式であることに注意してください。)
したがって、
$$ \mathbf{z}(x)=C_1\mathbf{y}_1(x)+C_2\mathbf{y}_2(x) $$
とおくと、同次連立1階線形微分方程式
$$ \begin{cases} \mathbf{z}'(x)=A(x)\mathbf{z}(x) \\ \mathbf{z}(x_0)=C_1\mathbf{v}_1+C_2\mathbf{v}_2 \end{cases} $$
は定理1より、 \( x=x_0 \) の近傍でただ一つの解をもちます。
よって、解の一意性から
$$ \mathbf{y}(x)=\mathbf{z}(x)=C_1\mathbf{y}_1(x)+C_2\mathbf{y}_2(x) $$
となり、 \( C_1,C_2 \) は初期値にのみ依存するので、一般解としては任意にとることができます。
今回はここまでです。お疲れ様でした。また次回にお会いしましょう。