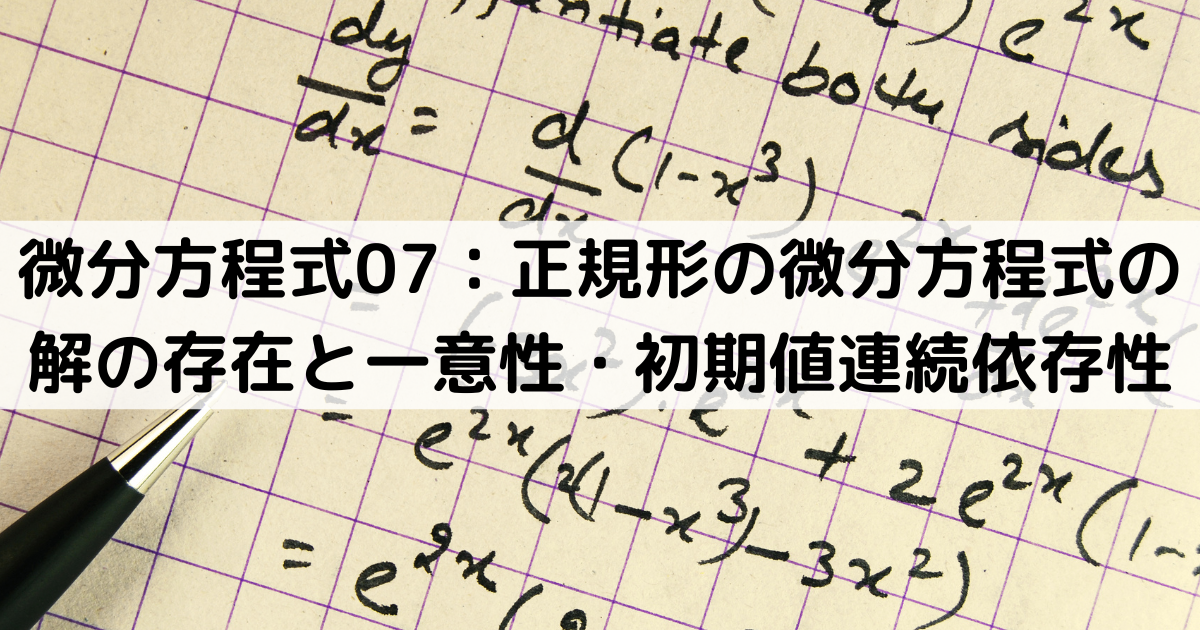こんにちは、ひかりです。
今回は微分方程式から正規形の微分方程式の解の存在と一意性・初期値連続依存性について解説していきます。
この記事では以下のことを紹介します。
- 正規形の微分方程式の解の存在と一意性について
- 正規形の微分方程式の初期値連続依存性について
正規形の微分方程式の解の存在と一意性
微分方程式06の記事にて、正規形の微分方程式を紹介して、具体的な正規形の微分方程式をピカールの逐次近似法で解くことを考えてみました。
今回は、一般の正規形の微分方程式に対して、解が存在することと解がただ1つであること(解の一意性)を示してみましょう。
引き続き、次の正規形の連立1階微分方程式の初期値問題を考えます。
$$ \begin{cases} \mathbf{y}'(x)=\mathbf{f}(x,\mathbf{y}(x)) \\ \mathbf{y}(x_0)=\mathbf{y}_0 \end{cases} $$
微分方程式06の定理1より、次の積分方程式の解の存在を示すことになります。
$$ \mathbf{y}(x)=\mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}(\xi))d\xi $$
まず、複素ベクトルの大きさについて定義しておきます。
\( n \) 次元複素ベクトル
$$ \mathbf{v}=\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}\in \mathbb{C}^n $$
に対して、ベクトル \( \mathbf{v} \) の大きさ \( \|\mathbf{v}\| \) を次で定める。
$$ \|\mathbf{v}\|=\left( \sum_{i=1}^n|v_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} $$
次に、解の存在と一意性の証明に必要な事柄について証明なしで簡単にまとめておきます。
(詳しくは別のシリーズで解説をする予定です。)
・実数全体の集合の部分集合 \( E\subset \mathbb{R} \) に対して、ある実数 \( M \) が存在して、任意の \( x\in E \) に対して \( x≦M \) となるとき、 \( E \) は上に有界という。
・また、上に有界な集合 \( E\subset \mathbb{R} \) に対して、次の2つをみたす実数 \( \alpha \) を \( E \) の上限といい、 \( \displaystyle \alpha=\sup E \) と表す。
(1) \( x≦\alpha, \ (x\in E) \)
(2) \( \gamma<\alpha \) ならば、 \( \gamma<x \) となる \( x\in E \) が存在する。
・さらに、関数 \( f(x) \) に対して、 \( x\in E \) での関数 \( f(x) \) の上限を
$$ \sup \{ f(x) \ | \ x\in E \} $$
で定義して、 \( \displaystyle \sup_{x\in E}f(x) \) と表す。
・1つ1つが関数であるような列 \( (f_n(x))_{n=1}^{\infty} \) を関数列という。
・関数列 \( (f_n(x))_{n=1}^{\infty} \) が集合 \( E \) 上である関数 \( f(x) \) に一様収束することを次をみたすことで定める。
$$ \lim_{n\to \infty}\sup_{x\in E}|f_n(x)-f(x)|=0 $$
連続関数の関数列 \( (f_n(x))_{n=1}^{\infty} \) の一様収束極限 \( f(x) \) も連続である。
関数列 \( (f_n(x))_{n=1}^{\infty} \) が
$$ \sup_{x\in E}|f_n(x)|≦M_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty}M_n<\infty $$
をみたすとき、 \( \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}f_n(x) \) は \( E \) 上のある関数に一様収束する。
無限級数 \( \displaystyle \sum{n=1}^{\infty}a_n \) が絶対収束するならば、収束する。つまり、
$$ \sum_{n=1}^{\infty}|a_n|<\infty \ \Rightarrow \ \sum_{n=1}^{\infty}a_n<\infty $$
区間 \( [a,b] \) 上の1変数の連続なベクトル値関数 \( \mathbf{v}(x) \) に対して、次が成り立つ。
$$ \left\| \int_a^b\mathbf{v}(\xi)d\xi \right\|≦\left| \int_a^b \|\mathbf{v}(\xi)\|d\xi \right| $$
それではいよいよ解の存在と一意性について示していきましょう。
$$ x_0\in \mathbb{R}, \quad r>0, \quad \rho>0, \quad \mathbf{y}_0\in \mathbb{C}^n $$
を固定する。また、 \( \mathbf{f}(x,\mathbf{y}) \) は
$$ |x-x_0|<r, \quad \|\mathbf{y}-\mathbf{y}_0\|≦\rho, \quad \|\mathbf{z}-\mathbf{y}_0\|≦\rho $$
をみたす任意の
$$ x\in \mathbb{R}, \quad \mathbf{y}\in \mathbb{C}^n, \quad \mathbf{z}\in \mathbb{C}^n $$
に対して、
$$ \|\mathbf{f}(x,\mathbf{y})\|≦M, \quad (有界性) $$
$$ \|\mathbf{f}(x,\mathbf{y})-\mathbf{f}(x,\mathbf{z})\|≦L\|\mathbf{y}-\mathbf{z}\|, \quad (リプシッツ条件) $$
をみたすとする。ただし、 \( M,L \) は \( x,\mathbf{y},\mathbf{z} \) に依らない定数である。
このとき、積分方程式
$$ \mathbf{y}(x)=\mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}(\xi))d\xi $$
の解は \( |x-x_0|≦\min\{r,\frac{\rho}{M}\} \) においてただ一つ存在する。
定理5の証明(気になる方だけクリックしてください)
(存在性) ピカールの逐次近似法で示します。そのため、
$$ \begin{cases} \mathbf{y}_0(x)=\mathbf{y}_0 \\ \displaystyle \mathbf{y}_k(x)=\mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}_{k-1}(\xi))d\xi \end{cases} $$
で関数列 \( (\mathbf{y}_k(x))_{k=0}^{\infty} \) を定義します。
(これが定理の仮定をみたすように定義されるかについては、証明後の注意をご覧ください)
このとき、 \( \displaystyle \lim_{k\to\infty}\mathbf{y}_k(x) \) の存在を示します。
$$ \mathbf{y}_k(x)=\mathbf{y}_0(x)+(\mathbf{y}_1(x)-\mathbf{y}_0(x))+\cdots+(\mathbf{y}_k(x)-\mathbf{y}_{k-1}(x)) $$
より、
$$ \|\mathbf{y}_k(x)\|≦\|\mathbf{y}_0(x)\|+\sum_{j=1}^k\|\mathbf{y}_j(x)-\mathbf{y}_{j-1}(x)\| $$
であるので、
$$ \sum_{j=1}^{\infty}\|\mathbf{y}_j(x)-\mathbf{y}_{j-1}(x)\|<\infty \tag{1} $$
が示せれば、定理3より、
$$ \mathbf{y}_0(x)+\sum_{j=1}^{\infty}(\mathbf{y}_j(x)-\mathbf{y}_{j-1}(x)) \tag{2} $$
の収束がいえます。それでは、式(1)を示しましょう。まず、
$$ \mathbf{y}_1(x)-\mathbf{y}_0(x)=\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}_0(\xi))d\xi $$
であるので、定理4と定理の仮定の有界性より、
$$ \begin{align} \|\mathbf{y}_1(x)-\mathbf{y}_0(x)\|&≦\left| \int_{x_0}^x\|\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}_0(\xi))\|d\xi \right| \\ &≦M|x-x_0| \end{align} \tag{3} $$
同様に、 \( j≧2 \) のときは
$$ \mathbf{y}_j(x)=\mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}_{j-1}(\xi))d\xi $$
$$ \mathbf{y}_{j-1}(x)=\mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}_{j-2}(\xi))d\xi $$
より、
$$ \mathbf{y}_j(x)-\mathbf{y}_{j-1}(x)=\int_{x_0}^x\{\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}_{j-1}(\xi))-\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}_{j-2}(\xi))\}d\xi $$
であるので、定理4と定理の仮定のリプシッツ条件より、
$$ \begin{align} \|\mathbf{y}_j(x)-\mathbf{y}_{j-1}(x)\|&≦\left| \int_{x_0}^x\|\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}_{j-1}(\xi))-\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}_{j-2}(\xi))\|d\xi \right| \\ &≦\left|\int_{x_0}^xL\|\mathbf{y}_{j-1}(x)-\mathbf{y}_{j-2}(x)\|d\xi \right| \end{align} \tag{4} $$
式(3)と式(4)より、
$$ \|\mathbf{y}_j(x)-\mathbf{y}_{j-1}(x)\|≦\frac{ML^{j-1}}{j!}|x-x_0|^j=\frac{M}{L}\frac{(L|x-x_0|)^j}{j!} $$
したがって、
$$ \begin{align} \sum_{j=1}^{\infty}\|\mathbf{y}_j(x)-\mathbf{y}_{j-1}(x)\|&≦\frac{M}{L}\sum_{j=1}^{\infty}\frac{L|x-x_0|)^j}{j!} \\ &=\frac{M}{L}(e^{L|x-x_0|}-1)<\infty \end{align} $$
よって、式(1)が示せたので、級数(2)は収束します。
次に、この級数(2)が一様収束することを示します。
$$ \|\mathbf{y}_j(x)-\mathbf{y}_{j-1}(x)\|≦\frac{ML^{j-1}}{j!}|x-x_0|^j $$
より、 \( K=\min \{r,\frac{\rho}{M}\} \) とおくと、
$$ \sup_{|x-x_0|≦K}\|\mathbf{y}_j(x)-\mathbf{y}_{j-1}(x)\|≦\frac{ML^{j-1}}{j!}K^j $$
(\( K=\min \{r,\frac{\rho}{M}\} \) とおく理由は証明後の注意をご覧ください。)
また、
$$ \sum_{j=1}^{\infty}\frac{ML^{j-1}}{j!}K^j=\frac{M}{L}\sum_{j=1}^{\infty}\frac{(KL)^j}{j!}=\frac{M}{L}(e^{KL}-1)<\infty $$
であるので、定理2より、 \( \mathbf{y}_k(x) \) は級数(2)つまり、 \( \displaystyle \mathbf{y}(x)=\lim_{k\to\infty}\mathbf{y}_k(x) \) に一様収束します。
したがって、 \( \mathbf{y}_k(x) \) は連続であるので、定理1より \( \mathbf{y}(x) \) も連続となります。
また、リプシッツ条件より、 \( \mathbf{f}(x,\mathbf{y}) \) は \( \mathbf{y} \) について連続となります。
したがって、
$$ \begin{align} \mathbf{y}(x)&=\lim_{k\to\infty}\mathbf{y}_k(x)=\lim_{k\to\infty}\left( \mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}_{k-1}(\xi))d\xi \right) \\ &=\mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x \lim_{k\to\infty}\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}_{k-1}(\xi))d\xi \\ & \quad (\mathbf{y}_kは\mathbf{y}に一様収束するので、積分と極限の交換ができます) \\ &=\mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\lim_{k\to\infty}\mathbf{y}_{k-1}(\xi))d\xi \quad (\mathbf{f}:連続) \\ &=\mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}(\xi))d\xi \end{align} $$
であるので、存在性がいえました。
(一意性) 積分方程式の2つの解を
$$ \begin{cases} \displaystyle \mathbf{y}(x)=\mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}(\xi))d\xi \\ \displaystyle \widetilde{\mathbf{y}}(x)=\mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\widetilde{\mathbf{y}}(\xi))d\xi \end{cases} $$
とおきます。
このとき、
$$ \mathbf{z}(x)=\mathbf{y}(x)-\widetilde{\mathbf{y}}(x)=\int_{x_0}^x\{ \mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}(\xi))-\mathbf{f}(\xi,\widetilde{\mathbf{y}}(\xi))\}d\xi $$
として、 \( \mathbf{z}(x)\equiv 0 \) を示します。
\( x≧x_0 \) とすると、定理4とリプシッツ条件より、
$$ \begin{align} \|\mathbf{z}(x)\|&≦\left| \int_{x_0}^x\|\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}(\xi))-\mathbf{f}(\xi,\widetilde{\mathbf{y}}(\xi))\|d\xi \right| \\ &≦L\left| \int_{x_0}^x\|\mathbf{y}(\xi)-\widetilde{\mathbf{y}}(\xi)\|d\xi \right| \\ &=L\left|\int_{x_0}^x\|\mathbf{z}(\xi)\|d\xi \right| \tag{5} \end{align} $$
\( \mathbf{y}(x),\widetilde{\mathbf{y}}(x) \) は連続なので、 \( \mathbf{z}(x) \) も連続となります。
よって、最大値の定理より、 \( \displaystyle N=\max_{|x-x_0|≦K}\|\mathbf{z}(x)\| \) が存在します。
したがって、
$$ \|\mathbf{z}(x)\|≦L\left|\int_{x_0}^x \|\mathbf{z}(\xi)\|d\xi \right|≦LN|x-x_0| \tag{6} $$
式(6)を式(5)の右辺に再び代入すると、
$$ \|\mathbf{z}(x)\|≦L\left| \int_{x_0}^x\|\mathbf{z}(\xi)\|d\xi \right|≦\frac{1}{2}LN^2|x-x_0|^2 $$
繰り返すと、
$$ \|\mathbf{z}(x)\|≦\frac{1}{p!}LN^p|x-x_0|^p \quad (p=1,2,\cdots) $$
\( |x-x_0|≦K \) より、
$$ \|\mathbf{z}(x)\|≦\frac{1}{p!}LN^pK^p \quad (p=1,2,\cdots) $$
\( p\to\infty \) とすると、 \( \mathbf{z}(x)\equiv 0 \) が得られます。
正規形の微分方程式の初期値連続依存性
次に、正規形の連立1階微分方程式の初期値問題
$$ \begin{cases} \mathbf{y}'(x)=\mathbf{f}(x,\mathbf{y}(x)) \\ \mathbf{y}(x_0)=\mathbf{y}_0 \end{cases} $$
の初期値 \( \mathbf{y}_0 \) が連続的に動いたとき、解 \( \mathbf{y}(x) \) も連続的に動くこと(解の初期値連続依存性)を示していきます。
これはつまり、初期値が近い2つの初期値問題の解も近いということを意味しています。
まず、次の補題を示します。
\( a(t),\varphi(t) \) を区間 \( I=[t_0,t_1] \) で定義された連続関数で \( a(t)≧0 \) とする。
このとき、 \( t\in I \) と定数 \( b \) に対して、不等式
$$ \varphi(t)≦b+\int_{t_0}^ta(s)\varphi(s)ds \tag{7} $$
が成り立つならば、次が成り立つ。
$$ \varphi(t)≦b\exp \left( \int_{t_0}^ta(s)ds \right) $$
定理6の証明(気になる方だけクリックしてください)
$$ F(t)=b+\int_{t_0}^ta(s)\varphi(s)ds $$
とおくと、仮定の不等式(7)より、
$$ F'(t)=a(t)\varphi(t)≦a(t)F(t) $$
両辺に \( \exp\left( -\int_{t_0}^ta(s)ds \right) \) をかけると、
$$ F'(t)\exp\left( -\int_{t_0}^ta(s)ds \right)-a(t)F(t)\exp\left( -\int_{t_0}^ta(s)ds \right)≦0 $$
となるので、これはつまり、
$$ \left\{ F(t)\exp\left( -\int_{t_0}^ta(s)ds \right) \right\}’≦0 $$
したがって、関数 \( \displaystyle F(t)\exp\left( -\int_{t_0}^ta(s)ds \right) \) は区間 \( I \) 上で \( t \) に関して単調減少となるので、
$$ \begin{align} F(t)\exp\left( -\int_{t_0}^ta(s)ds \right)&≦F(t_0)\exp\left( -\int_{t_0}^{t_0}a(s)ds \right) \\ &=F(t_0)=b \end{align} $$
よって、
$$ F(t)≦b\exp\left( \int_{t_0}^ta(s)ds \right) $$
であるので、仮定の不等式(7)より、
$$ \varphi(t)≦F(t)≦b\exp\left( \int_{t_0}^ta(s)ds \right) $$
となり、定理6が成り立ちます。
それでは、解の初期値連続依存性を示していきましょう。
定理5と同じ仮定の下、正規形の連立1階微分方程式の初期値問題
$$ \begin{cases} \mathbf{y}'(x)=\mathbf{f}(x,\mathbf{y}(x)) \\ \mathbf{y}(x_0)=\mathbf{y}_0 \end{cases} \tag{8} $$
を考える。このとき、
$$ \|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|\to 0, \quad (n\to\infty) $$
となる初期値の列 \( (\mathbf{y}^n_0)_{n=1}^{\infty} \) を考えて、 \( \mathbf{y}^n_0 \) を初期値とする方程式(8)の解を \( \mathbf{y}^n(x) \) とおくと、解の存在する範囲の任意の \( x \) に対して、
$$ \|\mathbf{y}^n(x)-\mathbf{y}(x)\|\to 0, \quad (n\to \infty) $$
となる。
定理7の証明(気になる方だけクリックしてください)
\( \mathbf{y}^n(x),\mathbf{y}(x) \) はそれぞれ積分方程式
$$ \mathbf{y}^n(x)=\mathbf{y}^n_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}^n(\xi))d\xi $$
$$ \mathbf{y}(x)=\mathbf{y}_0+\int_{x_0}^x\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}(\xi))d\xi $$
をみたします。よって、差をとると、
$$ \mathbf{y}^n(x)-\mathbf{y}(x)=(\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0)+\int_{x_0}^x\{\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}^n(\xi))-\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}(\xi))\}d\xi $$
したがって、定理4とリプシッツ条件より、
$$ \begin{align} \|\mathbf{y}^n(x)-\mathbf{y}(x)\|&≦\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|+\left| \int_{x_0}^x\|\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}^n(\xi))-\mathbf{f}(\xi,\mathbf{y}(\xi))\|d\xi \right| \\ &≦\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|+L\left| \int_{x_0}^x\|\mathbf{y}^n(\xi)-\mathbf{y}(\xi)\|d\xi \right| \end{align} $$
(i) \( x≧x_0 \) のとき
このときは、
$$ \|\mathbf{y}^n(x)-\mathbf{y}(x)\|≦\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|+L\int_{x_0}^x\|\mathbf{y}^n(\xi)-\mathbf{y}(\xi)\|d\xi $$
であるので、
$$ \varphi(x)=\|\mathbf{y}^n(x)-\mathbf{y}(x)\|, \ b=\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|, \ a(x)=L $$
とおけば、グロンウォールの不等式より、
$$ \begin{align} \|\mathbf{y}^n(x)-\mathbf{y}(x)\|&≦\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|\exp\left( \int_{x_0}^xLd\xi \right) \\ &=\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|e^{L(x-x_0)} \end{align} $$
(ii) \( x<x_0 \) のとき
このときは、
$$ \|\mathbf{y}^n(x)-\mathbf{y}(x)\|≦\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|-L\int_{x_0}^x\|\mathbf{y}^n(\xi)-\mathbf{y}(\xi)\|d\xi $$
であるので、
$$ u=x_0+(x_0-x)=2x_0-x $$
とおくと、 \( u>x_0 \) であり、
$$ \begin{align} &\|\mathbf{y}^n(2x_0-u)-\mathbf{y}(2x_0-u)\| \\ &≦\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|+L\int_{x_0}^u\|\mathbf{y}^n(2x_0-\eta)-\mathbf{y}(2x_0-\eta)\|d\eta \end{align} $$
よって、
$$ \varphi(x)=\|\mathbf{y}^n(x)-\mathbf{y}(x)\|, \ b=\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|, \ a(x)=L $$
とおけば、
$$ \varphi(2x_0-u)≦b+\int_{x_0}^ua(2x_0-\eta)\varphi(2x_0-\eta)d\eta $$
となるので、グロンウォールの不等式より、
$$ \begin{align} \varphi(x)&=\varphi(2x_0-u)≦b\exp\left(\int_{x_0}^ua(2x_0-\eta)d\eta\right) \\ &=b\exp\left(\left|\int_{x_0}^xa(\xi)d\xi\right|\right) \end{align} $$
したがって、
$$ \|\mathbf{y}^n(x)-\mathbf{y}(x)\|≦\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|e^{L|x-x_0|} $$
つまり、(i)と(ii)のどちらの場合でも
$$ \begin{align} \|\mathbf{y}^n(x)-\mathbf{y}(x)\|&≦\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|e^{L|x-x_0|} \\ &≦\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}_0\|e^{Lr} \quad (|x-x_0|<rより) \\ &\to 0 \quad (n\to\infty) \quad (\|\mathbf{y}^n_0-\mathbf{y}\|\to 0より) \end{align} $$
したがって、定理が成り立ちます。
今回はここまでです。お疲れ様でした。また次回にお会いしましょう。