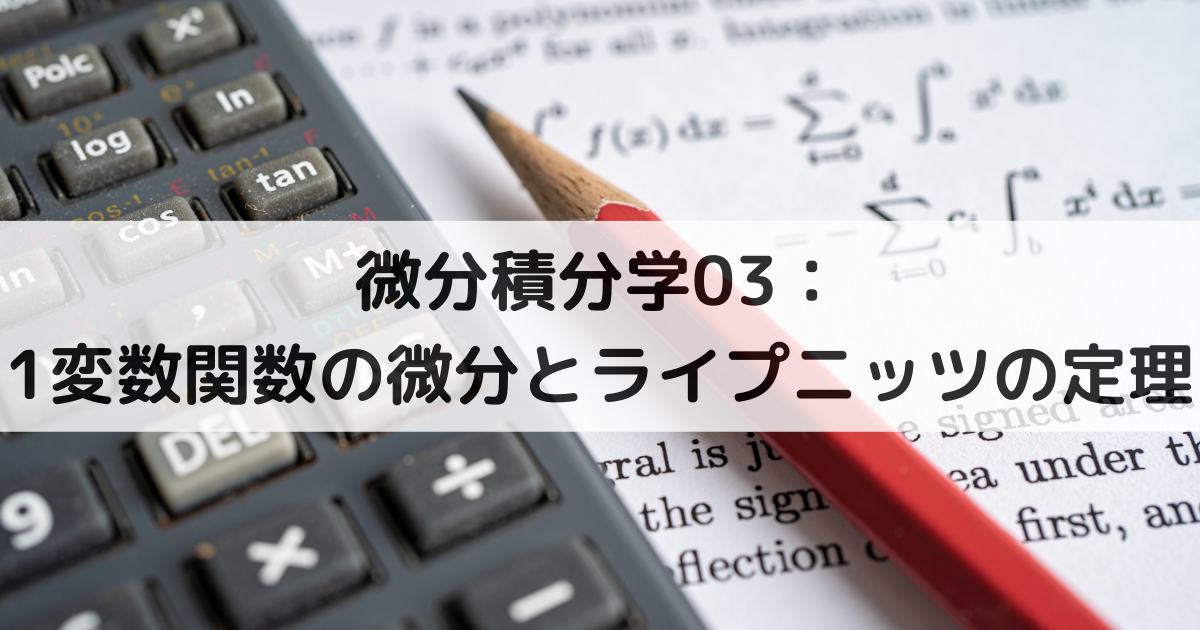こんにちは、ひかりです。
今回は微分積分学から1変数関数の微分とライプニッツの定理について解説していきます。
この記事では以下のことを紹介します。
- 1変数関数の極限・連続性・微分に関する復習
- さまざまな関数の導関数のまとめ
- 高階導関数とライプニッツの定理について
1変数関数の極限・連続性・微分
ここでは、高校数学で勉強した極限・連続性・微分の知識について簡単にまとめてみたいと思います。
詳しく知りたい方は下の高校数学(数学Ⅲ)05-07の記事をご覧ください。
1変数関数の極限
関数 \( y=f(x) \) がある点 \( a \) の近くのすべての点 \( x \) で定義されているとします。
ただし、 \( x=a \) で \( f(a) \) が定義されていなくても問題ないです。
関数 \( f(x) \) において、 \( x \) が \( a \) とは異なる値をとりながら限りなく \( a \) に近づくとき、 \( f(x) \) が一定の値 \( \alpha \) に限りなく近づくとする。このとき、 \( x\to a \) のとき \( f(x) \) は \( \alpha \) に収束するといい、
$$ \lim_{x\to a}f(x)=\alpha \quad \text{または} \quad f(x)\to \alpha \ (x\to a) $$
と表し、 \( \alpha \) を \( x\to a \) のときの \( f(x) \) の極限値という。
関数 \( f(x),g(x) \) が収束して、 \( \displaystyle \lim_{x\to a}f(x)=\alpha, \ \lim_{x\to a}g(x)=\beta \) のとき、次が成り立つ。
(1) \( \displaystyle \lim_{x\to a}kf(x)=k\alpha \quad (k\text{は定数}) \)
(2) \( \displaystyle \lim_{x\to a}(f(x)+g(x))=\alpha+\beta \)
\( \displaystyle \lim_{x\to a}(f(x)-g(x))=\alpha-\beta \)
(3) \( \displaystyle \lim_{x\to a}f(x)g(x)=\alpha\beta \)
(4) \( \displaystyle \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\alpha}{\beta} \quad (\beta\not=0) \)
(1) 関数 \( f(x) \) において、 \( x \) が \( a \) とは異なる値をとりながら限りなく \( a \) に近づくとき、 \( f(x) \) が限りなく大きくなるとする。このとき、 \( x\to a \) のとき \( f(x) \) は正の無限大に発散するといい、
$$ \lim_{x\to a}f(x)=\infty \quad \text{または} \quad f(x)\to \infty \ (x\to a) $$
と表す。
(2) 関数 \( f(x) \) において、 \( x \) が \( a \) とは異なる値をとりながら限りなく \( a \) に近づくとき、 \( f(x) \) の値が負でその絶対値 \( |f(x)| \) が限りなく大きくなるとする。このとき、 \( x\to a \) のとき \( f(x) \) は負の無限大に発散するといい、
$$ \lim_{x\to a}f(x)=-\infty \quad \text{または} \quad f(x)\to -\infty \ (x\to a) $$
と表す。
(1) 関数 \( f(x) \) において、 \( x \) が \( a \) より大きい値をとって限りなく \( a \) に近づくとき、 \( f(x) \) が一定の値 \( \alpha \) に限りなく近づくとする。このとき、 \( \alpha \) を \( x \) を右側から \( a \) に近づくときの \( f(x) \) の極限値といい、 \( \displaystyle \lim_{x\to a+0}f(x)=\alpha \) とかく。
(2) 関数 \( f(x) \) において、 \( x \) が \( a \) より小さい値をとって限りなく \( a \) に近づくとき、 \( f(x) \) が一定の値 \( \alpha \) に限りなく近づくとする。このとき、 \( \alpha \) を \( x \) を左側から \( a \) に近づくときの \( f(x) \) の極限値といい、 \( \displaystyle \lim_{x\to a-0}f(x)=\alpha \) とかく。
(1) \( x\to\infty \) のときに \( f(x) \) の値が限りなく \( \alpha \) に近づくとき、 \( \displaystyle \lim_{x\to\infty}f(x)=\alpha \) と表す。
(2) \( x\to-\infty \) のときに \( f(x) \) の値が限りなく \( \alpha \) に近づくとき、 \( \displaystyle \lim_{x\to-\infty}f(x)=\alpha \) と表す。
(1) 関数 \( f(x), \ g(x) \) が \( a \) の近くで \( f(x)≦ g(x) \) が成り立ち、
$$ \lim_{x\to a}f(x)=\alpha, \quad \lim_{x\to a}g(x)=\beta $$
ならば、 \( \alpha≦\beta \)
(2) (はさみうちの原理)
関数 \( f(x), \ g(x), \ h(x) \) が \( a \) の近くで \( f(x)≦ g(x)≦ h(x) \) が成り立ち、
$$ \lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}h(x)=\alpha $$
ならば、 \( \displaystyle \lim_{x\to a}g(x)=\alpha \)
1変数関数の連続性
区間 \( I \) 上の関数 \( f(x) \) と \( a\in I \) (つまり、 \( I \) 上の点 \( a \) )に対して、
$$ \lim_{x\to a}f(x)=f(a) $$
が成り立つとき、 \( f \) は点 \( a \) で連続であるという。
また、すべての \( a\in I \) で \( f \) が連続であるとき、 \( f \) は \( I \) 上連続であるという。
定理1をもちいることで、連続関数の和・積・商も連続関数であることが次のような形でいえます。
\( f,g \) を \( I \) 上連続な関数として、 \( a\in I, \ k,\ell \) を実数とする。
(1) \( kf(x)+\ell g(x) \) も \( I \) 上連続であり、次が成り立つ。
$$ \lim_{x\to a}(kf(x)+\ell g(x))=kf(a)+\ell g(a) $$
(2) \( f(x)g(x) \) も \( I \) 上連続であり、次が成り立つ。
$$ \lim_{x\to a}f(x)g(x)=f(a)g(a) $$
(3) すべての \( x\in I \) に対して、 \( g(x)\not=0 \) のとき、 \( \frac{f(x)}{g(x)} \) も \( I \) 上連続であり、次が成り立つ。
$$ \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(a)}{g(a)} $$
関数 \( y=x^n, \ (n=1,2,\dots,n) \) は \( \mathbb{R} \) 上連続である。
(大学数学では実数全体の集合を \( \mathbb{R} \) で表します。)
よって、それらの和である
$$ y=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0 \quad (a_n,\dots,a_0 は実数) $$
も \( \mathbb{R} \) 上連続である。
また、2つの連続関数の合成関数も連続関数となることが次のような形でいえます。
\( f \) を区間 \( I \) 上の連続関数、 \( g \) を区間 \( J \) 上の連続関数とする。
また、\( f,g \) を合成可能な関数(つまり \( f \) の値域を \( f(I) \) とおくと、 \( f(I)\subset J \) (\( f(I) \) は \( J \) の部分集合))とする。
このとき、合成関数 \( (g\circ f)(x) \) も \( I \) 上連続であり、次が成り立つ。
$$ \lim_{x\to a}g\circ f(x)=g\circ f(a) $$
定理4の証明(気になる方だけクリックしてください)
まず、連続性とは次を表すことに注意しましょう。
$$ \lim_{x\to a}f(x)=f(a)=f(\lim_{x\to a}x) $$
これを用いると、
$$ \begin{align} \lim_{x\to a}g\circ f(x)&=\lim_{x\to a}g(f(x)) \\ &=g(\lim_{x\to a}f(x)) \quad (gは連続関数) \\ &=g(f(\lim_{x\to a}x)) \quad (fは連続関数) \\ &=g(f(a))=g\circ f(a) \end{align} $$
\( f(x)=1+x^2, \ g(y)=\log y \) とする。このとき、 \( f \) は \( \mathbb{R} \) 上連続であり、 \( g \) は \( (0,\infty) \) 上で連続である。
また、 \( f \) の値域 \( f(I) \) は区間 \( [1,\infty) \) であるので、 \( f(I)\subset J \) より \( f,g \) は合成可能である。
よって、合成関数 \( g\circ f(x)=\log (1+x^2) \) も \( \mathbb{R} \) 上連続となる。
最後に、連続関数に対する最大値・最小値の原理と中間値の定理を復習しましょう。
閉区間 \( [a,b] \ (-\infty<a<b<\infty) \) 上で連続な関数は、その区間上で最大値・最小値をもつ。
関数 \( f(x) \) が閉区間 \( [a,b] \) 上連続で \( f(a)\not=f(b) \) ならば、 \( f(a) \) と \( f(b) \) の間の任意の値 \( m \) に対して、
$$ f(c)=m \quad (a<c<b) $$
となる \( c \) が少なくとも1つ存在する。
1変数関数の微分
$$ \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} $$
を関数 \( y=f(x) \) の \( x=a \) における微分係数といい、 \( f'(a) \) で表す。
また、このとき \( f(x) \) は \( x=a \) で微分可能であるという。
さらに区間 \( I \) に対して、\( f(x) \) がすべての \( x\in I \) で微分可能であるとき、 \( f \) は \( I \) 上微分可能であるという。
微分可能性と連続性との関係として、次のようなことが成り立ちます。
関数 \( f(x) \) が \( x=a \) で微分可能ならば、 \( f(x) \) は \( x=a \) において連続となる。
よって、関数 \( f(x) \) が \( I \) 上微分可能ならば、 \( f(x) \) は \( I \) 上連続となる。
関数 \( y=f(x) \) に対して、 \( x \) に \( f'(x) \) を対応させて得られる関数を \( f(x) \) の導関数といい、 \( f'(x), \ y’, \ \frac{dy}{dx} \) などと書く。つまり、
$$ f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} $$
また、関数の導関数を求めることを、関数を微分するという。
\( f(x), \ g(x) \) が微分可能な関数のとき、
(1) \( (c)’=0, \quad (c:\text{定数}) \)
(2) \( \{ kf(x)\}’=kf'(x), \quad (k:\text{定数}) \)
(3) \( \{ f(x)+g(x) \}’=f'(x)+g'(x) \)
(4) \( \{ f(x)-g(x) \}’=f'(x)-g'(x) \)
さまざまな関数の導関数
ここでは、高校数学で勉強したさまざまな関数の導関数の知識について簡単にまとめてみたいと思います。
詳しく知りたい方は下の記事をご覧ください。
まずは、積・商の微分公式について見ていきましょう。
(1) (積の微分公式)
\( f(x), \ g(x) \) を \( I \) 上微分可能な関数とすると、 \( f(x)g(x) \) も \( I \) 上微分可能な関数であり、
$$ \{ f(x)g(x) \}’=f'(x)g(x)+f(x)g'(x) $$
(2) (商の微分公式)
\( f(x), \ g(x) \) を \( I \) 上微分可能な関数ですべての \( x\in I \) に対して \( g(x)\not=0 \) とすると、 \( \frac{f(x)}{g(x)} \) も \( I \) 上微分可能な関数であり、
$$ \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}’=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2} $$
とくに、
$$ \left\{ \frac{1}{g(x)} \right\}’=-\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2} $$
合成関数・逆関数の微分公式も見ていきましょう。
(1) (合成関数の微分公式)
\( y=f(x) \) を区間 \( I \) 上微分可能な関数、 \( z=g(y) \) を区間 \( J \) 上微分可能な関数で \( f(I)\subset J \) をみたすとする。
このとき、合成関数 \( y=g(f(x)) \) も \( I \) 上微分可能な関数であり、
$$ \{ g(f(x)) \}’=g'(f(x))f'(x) $$
いいかえると、
$$ \frac{dz}{dx}=\frac{dz}{dy}\cdot\frac{dy}{dx} $$
(2) (逆関数の微分公式)
微分可能な関数 \( y=f(x) \) が逆関数 \( x=f^{-1}(y) \) をもつとき、
$$ (f^{-1})'(y)=\frac{1}{f'(x)} $$
いいかえると、
$$ \frac{dx}{dy}=\frac{1}{\frac{dy}{dx}} $$
これらの公式をもとに、高校数学ではさまざまな関数の導関数を求めてきました。
それらを一覧にしておきましょう。
| \( y=f(x) \) | \( y’=f'(x) \) |
| \( y=c \quad (c:定数) \) | \( y’=0 \) |
| \( y=x^{\alpha} \quad (\alpha:実数) \) | \( y’=\alpha x^{\alpha-1} \) |
| \( y=e^x \) | \( y’=e^x \) |
| \( y=a^x \quad (a>0, \ a\not=1) \) | \( y’=a^x\log a \) |
| \( y=\log|x| \) | \( y’=\frac{1}{x} \) |
| \( y=\sin x \) | \( y’=\cos x \) |
| \( y=\cos x \) | \( y’=-\sin x \) |
| \( y=\tan x \) | \( y’=\frac{1}{\cos^2 x} \) |
これに加えて大学数学にて初めて登場した逆三角関数と双曲線関数の導関数もまとめてみましょう。
表の後の例にて、いくつかの関数の導関数を実際に求めています。
| \( y=f(x) \) | \( y’=f'(x) \) |
| \( y=\sin^{-1}x \) | \( y’=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \) |
| \( y=\cos^{-1}x \) | \( y’=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \) |
| \( y=\tan^{-1}x \) | \( y’=\frac{1}{1+x^2} \) |
| \( y=\sinh x \) | \( y’=\cosh x \) |
| \( y=\cosh x \) | \( y’=\sinh x \) |
| \( y=\tanh x \) | \( y’=\frac{1}{\cosh^2 x} \) |
| \( y=\sinh^{-1}x \) | \( y’=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \) |
| \( y=\cosh^{-1}x \) | \( y’=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \) |
| \( y=\tanh^{-1}x \) | \( y’=\frac{1}{1-x^2} \) |
(1) \( \tan^{-1}x \) の導関数を求める。
\( y=\tan x \) とおくと、
$$ y’=\frac{1}{\cos^2 x}=1+\tan^2x=1+y^2 $$
よって、逆関数の微分公式より、
$$ (\tan^{-1}y)’=\frac{1}{y’}=\frac{1}{1+y^2} $$
\( y \) と \( x \) を置き換えると、
$$ (\tan^{-1}x)’=\frac{1}{1+x^2} $$
(2) \( \cosh x \) の導関数を求める。
定義より \( \cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2} \) であるので、
$$ (\cosh x)’=\left( \frac{e^x+e^{-x}}{2} \right)’=\frac{(e^x)’+(e^{-x})’}{2}=\frac{e^x-e^{-x}}{2}=\sinh x $$
(3) \( \sinh^{-1}x \) の導関数を求める。
\( y=\sinh^{-1} x \) とおくと、 \( x=\sinh y=\frac{e^y-e^{-y}}{2} \) となる。
ここで、 \( e^y=\theta \ (\theta>0) \) とおくと、
$$ e^yx=\frac{e^{2y}-1}{2}=\frac{\theta^2-1}{2} $$
よって、 \( e^yx=\theta x \) より、
$$ \theta^2-2x\theta-1=0 $$
\( \theta>0 \) に注意して解くと、 \( \theta=x+\sqrt{x^2+1} \) となる。
よって、
$$ \sinh^{-1}x=y=\log e^y=\log \theta=\log (x+\sqrt{x^2+1}) $$
合成関数の微分公式を用いてこれを微分すると、
$$ \begin{align} (\sinh^{-1}x)’&=\frac{(x+\sqrt{x^2+1})’}{x+\sqrt{x^2+1}}=\frac{1+\frac{1}{2}(x^2+1)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2x}{x+\sqrt{x^2+1}} \\ &=\frac{1+x(x^2+1)^{-\frac{1}{2}}}{x+\sqrt{x^2+1}} \\ &=\frac{\sqrt{x^2+1}+x}{(x+\sqrt{x^2+1})\sqrt{x^2+1}} \quad (分母分子に \sqrt{x^2+1} をかけた) \\ &=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad (x+\sqrt{x^2+1}で約分) \end{align} $$
高階導関数とライプニッツの定理
高階導関数
関数 \( y=f(x) \) が微分可能であり、その導関数 \( y’=f'(x) \) も微分可能であり、・・・と \( y=f(x) \) が順々に \( n \) 回微分することが可能であるとき、 \( y=f(x) \) を \( n \) 回微分して得られる関数を \( y \) の第 \( n \) 階導関数といい、
$$ y^{(n)}, \ f^{(n)}(x), \ \frac{d^nf}{dx^n}(x), \ \frac{d^n}{dx^n}f(x) $$
などと表します。
\( y=4x^3+3x^2+2x+1 \) とすると、
$$ y’=12x^2+6x+2, \quad y^{\prime\prime}=24x+6, \quad y^{(3)}=24, \quad y^{(4)}=0 $$
関数 \( y=f(x) \) が微分可能な回数に応じて、次のような呼び方を導入します。
関数 \( y=f(x) \) が \( f \) の定義域上連続であるとき、 \( f \) を \( C^0 \) 級関数という。
また、自然数 \( n \) に対して、 \( f \) が \( n \) 回微分可能であり、その第 \( n \) 階導関数 \( f^{(n)}(x) \) が \( f^{(n)} \) の定義域上連続であるとき、 \( f \) を \( C^n \) 級関数という。
さらに、 \( f \) が何回でも微分可能なとき、 \( f \) を \( C^{\infty} \) 級関数という。
(1) \( y=|x| \) は原点で微分不可能であるため、 \( C^0 \) 級関数である。
(2) \( f(x)= \begin{cases} x^2 & x≧0 \\ -x^2 & x<0 \end{cases} \) を考える。
微分すると、
$$ f'(x)= \begin{cases} 2x & x≧ 0 \\ -2x & x<0 \end{cases} $$
つまり、 \( f'(x)=2|x| \) となる。これは連続であるが微分不可能であるため、この関数は \( C^1 \) 級関数である。
(3) \( y=e^x \) は
$$ y’=e^x, \quad y^{\prime\prime}=e^x, \quad \cdots, \quad y^{(n)}=e^x, \quad \cdots $$
よって、 \( C^{\infty} \) 級関数である。
ライプニッツの定理
関数の積 \( fg \) の第 \( n \) 階導関数 \( (fg)^{(n)} \) の求め方として、次のライプニッツの定理があります。
2つの関数 \( f,g \) がどちらも \( n \) 回微分可能であるとき、次が成り立つ。
$$ \begin{align} (fg)^{(n)}&={}_nC_0f^{(n)}g+{}_nC_1f^{(n-1)}g’+{}_nC_2f^{(n-2)}g^{\prime\prime} \\ &\quad +\cdots +{}_nC_rf^{(n-r)}g^{(r)}+\cdots +{}_nC_nfg^{(n)} \end{align} $$
ここで、 \( {}_nC_r=\frac{n!}{r!(n-r)!} \) である。
定理11の証明(気になる方だけクリックしてください)
数学的帰納法にて示します。
\( n=1 \) のときは積の微分公式より、
$$ (fg)’=f’g+fg’={}_1C_0f’g+{}_1C_1fg’ $$
であるので、成り立ちます。
\( n=k \) のとき定理の式が成り立つと仮定するとき、 \( n=k+1 \) で示します。
帰納法の仮定より、第 \( k \) 階導関数 \( (fg)^{(k)} \) は次をみたします。
$$ \begin{align} (fg)^{(k)}&={}_kC_0f^{(k)}g+{}_kC_1f^{(k-1)}g’+{}_kC_2f^{(k-2)}g^{\prime\prime} \\ &\quad +\cdots +{}_kC_rf^{(k-r)}g^{(r)}+\cdots +{}_kC_kfg^{(k)} \end{align} $$
この式をもう一回微分すると、
$$ \begin{align} (fg)^{(k+1)}&={}_kC_0(f^{(k)}g)’+\color{red}{{}_kC_1(f^{(k-1)}g’)’}+{}_kC_2(f^{(k-2)}g^{\prime\prime})’ \\ &\quad +\cdots +{}_kC_r(f^{(k-r)}g^{(r)})’+\cdots +{}_kC_k(fg^{(k)})’ \\ &={}_kC_0f^{(k+1)}g+({}_kC_0+\color{red}{{}_kC_1})\color{red}{f^{(k)}g’}+(\color{red}{{}_kC_1}+{}_kC_2)\color{red}{f^{(k-1)}g^{\prime\prime}} \\ &\quad +\cdots +({}_kC_{r-1}+{}_kC_r)f^{(k-r+1)}g^{(r)}+\cdots +{}_kC_kfg^{(k+1)} \end{align} $$
ここで、
$$ {}_kC_{r-1}+{}_kC_r={}_{k+1}C_r, \quad {}_kC_0={}_{k+1}C_0, \quad {}_kC_k={}_{k+1}C_{k+1} $$
であるので、
$$ \begin{align} (fg)^{(k+1)}&={}_{k+1}C_0f^{(k+1)}g+{}_{k+1}C_1f^{(k)}g’+{}_{k+1}C_2f^{(k-1)}g^{\prime\prime} \\ &\quad +\cdots +{}_{k+1}C_rf^{(k-r+1)}g^{(r)}+\cdots +{}_{k+1}C_{k+1}fg^{(k+1)} \end{align} $$
よって、 \( n=k+1 \) の場合も定理の式が成り立ちます。
したがって、数学的帰納法よりこの定理が示せました。
\( y=x^2e^{ax} \) の第 \( n \) 階導関数を求める。
$$ (x^2)^{(n)}=0 \quad (n=3,4,\cdots) $$
であることに注意する。
\( f=e^{ax}, \ g=x^2 \) としてライプニッツの定理を用いると、
$$ \begin{align} (x^2e^{ax})^{(n)}&={}_nC_0(e^{ax})^{(n)}x^2+{}_nC_1(e^{ax})^{(n-1)}(x^2)’+{}_nC_2(e^{ax})^{(n-2)}(x^2)^{\prime\prime} \\ &\quad +\cdots +{}_nC_r(e^{ax})^{(n-r)}(x^2)^{(r)}+\cdots +{}_nC_n(e^{ax})(x^2)^{(n)} \\ &={}_nC_0a^ne^{ax}x^2+{}_nC_1a^{n-1}e^{ax}(2x)+{}_nC_2a^{n-2}e^{ax}\cdot 2 \\ &=a^nx^2e^{ax}+2na^{n-1}xe^{ax}+\frac{2n(n-1)}{2}a^{n-2}e^{ax} \\ &=a^{n-2}e^{ax}\{ a^2x^2+2anx+n(n-1)\} \end{align} $$
今回はここまでです。お疲れ様でした。また次回にお会いしましょう。