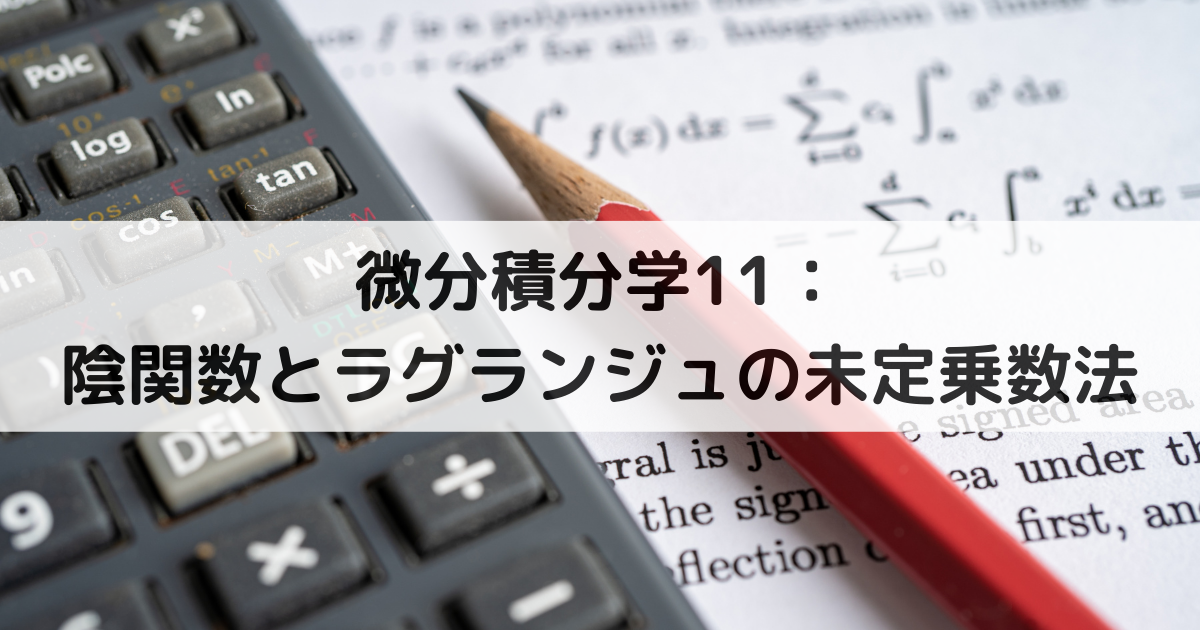こんにちは、ひかりです。
今回は微分積分学から陰関数とラグランジュの未定乗数法について解説していきます。
この記事では以下のことを紹介します。
- 陰関数の定義と陰関数定理について
- 条件付き極値とラグランジュの未定乗数法について
陰関数の定義と陰関数定理
円の方程式 \( x^2+y^2-1=0 \) のように、 \( F(x,y)=0 \) という関係式をみたしているものを考えます。
\( x^2+y^2=1 \) の場合は、 \( y \) について解くことで
$$ y=f(x)=\pm\sqrt{1-x^2} $$
というように、 \( y=f(x) \) の形で表現することができます。
この \( f(x) \) を \( x^2+y^2=1 \) の定める陰関数といいます。
一般に、次のように陰関数を定めます。
関数 \( y=f(x) \) が \( F(x,f(x))=0 \) をみたすとき、 \( y=f(x) \) を \( F(x,y)=0 \) の定める陰関数という。
ここで、注意が必要になるのが、 \( F(x,y)=0 \) はかならず陰関数 \( y=f(x) \) が存在して、 \( F(x,f(x))=0 \) となるわけではないということです。
\( F(x,y)=x^2+y^2=0 \) を考えると、これは1点 \( (x,y)=(0,0) \) になるので、陰関数が存在しない。
では、どのようなときに陰関数が存在するのでしょうか。
それを与えたのが次に紹介する陰関数定理となります。
\( F(x,y) \) を点 \( (a,b) \) の近くで定義された \( C^1 \) 級関数として、
$$ F(a,b)=0, \quad F_y(a,b)\not=0 $$
をみたすとする。
このとき、点 \( (a,b) \) の近くで、
$$ F(x,f(x))=0, \quad f(a)=b $$
をみたす陰関数 \( y=f(x) \) が存在する。さらに、 \( f(x) \) は微分可能であり、次が成り立つ。
$$ f'(x)=-\frac{F_x(x,f(x))}{F_y(x,f(x))} $$
$$ x^2+2xy+y^2=4 $$
の陰関数 \( y=f(x) \) の導関数 \( f’, \ f^{\prime\prime} \) を求める。
$$ F(x,y)=x^2+2xy+y^2-4 $$
とおくと、
$$ F_x(x,y)=2x+2y, \quad F_y(x,y)=2x+2y $$
となる。よって、陰関数定理より、
$$ f'(x)=-\frac{F_x(x,f(x))}{F_y(x,f(x))}=-\frac{2x+2y}{2x+2y}=-1, \quad f^{\prime\prime}=0 $$
条件付き極値とラグランジュの未定乗数法
微分積分学10の記事で関数 \( z=f(x,y) \) の極値の求め方を紹介しました。
今回は関数 \( z=f(x,y) \) が条件 \( g(x,y)=0 \) をみたしながら動くときの極値を求めていきましょう。
このような極値を条件付き極値といい、これを求めるための強力な定理がラグランジュの未定乗数法といわれる定理となります。
関数 \( f(x,y), \ g(x,y) \) はともに \( C^1 \) 級であるとする。
条件 \( g(x,y)=0 \) をみたしながら \( f(x,y) \) が動いたときに点 \( (a,b) \) で広義の極値をもつとする。
そして、変数 \( \lambda \) を用いて(この \( \lambda \) をラグランジュの未定乗数という)、
$$ F(x,y,\lambda)=f(x,y)-\lambda g(x,y) $$
とおく。このとき、 \( g_x(a,b) \) と \( g_y(a,b) \) の少なくとも一方が \( 0 \) でないならば、
$$ F_x(a,b,\lambda_0)=F_y(a,b,\lambda_0)=F_{\lambda}(a,b,\lambda_0)=0 \tag{1} $$
をみたす定数 \( \lambda_0 \) が存在する。
定理2の証明(気になる方だけクリックしてください)
ここでは、 \( g_y(a,b)\not=0 \) として示します。( \( g_x(a,b)\not=0 \) のときも同様に示せます)
まず、定理の仮定より、点 \( (a,b) \) は条件 \( g(x,y)=0 \) のもとでの広義の極値であるので、
$$ g(a,b)=0 $$
となります。よって、 \( g(a,b)=0, \ g_y(a,b)\not=0 \) であるので、陰関数定理より点 \( (a,b) \) の近くで、
$$ g(x,\varphi(x))=0, \quad \varphi(a)=b $$
をみたす陰関数 \( y=\varphi(x) \) が存在します。また、点 \( a \) での微分係数は
$$ \varphi'(a)=-\frac{g_x(a,\varphi(a))}{g_y(a,\varphi(a))}=-\frac{g_x(a,b)}{g_y(a,b)} $$
となります。この陰関数 \( y=\varphi(x) \) を用いると、定理の仮定より \( f(x,\varphi(x)) \) は \( x=a \) で広義の極値をもつことになります。
よって、微分積分学10の記事の定理4より、
$$ f_x(a,b)=f_y(a,b)=0 $$
となります。したがって、合成関数の微分から
$$ \begin{align} \frac{d}{dx}f(x,\varphi(x))|_{x=a}&=\frac{\partial}{\partial x}f(x,\varphi(x))|_{x=a}\frac{dx}{dx}|_{x=a}+\frac{\partial}{\partial y}f(x,\varphi(x))|_{x=a}\frac{dy}{dx}|_{x=a} \\ &=f_x(a,b)+f_y(a,b)\varphi'(a) \\ &=f_x(a,b)+f_y(a,b)\left(-\frac{g_x(a,b)}{g_y(a,b)} \right)=0 \end{align} $$
とくに、
$$ f_x(a,b)+f_y(a,b)\left(-\frac{g_x(a,b)}{g_y(a,b)} \right)=0 $$
であることを覚えておきましょう。よって、
$$ \lambda_0=\frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)}, \quad F(x,y,\lambda)=f(x,y)-\lambda g(x,y) $$
とおくと、
$$ \begin{align} F_x(a,b,\lambda_0)&=f_x(a,b)-\lambda_0 g_x(a,b)=f_x(a,b)-\frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)}\cdot g_x(a,b) \\ &=f_x(a,b)+f_y(a,b)\left(-\frac{g_x(a,b)}{g_y(a,b)} \right)=0 \end{align} $$
$$ \begin{align} F_y(a,b,\lambda_0)&=f_y(a,b)-\lambda_0 g_y(a,b)=f_y(a,b)-\frac{f_y(a,b)}{g_y(a,b)}\cdot g_y(a,b) \\ &=f_y(a,b)-f_y(a,b)=0 \end{align} $$
また、 \( g(a,b)=0 \) であったことを思い出すと、
$$ F_{\lambda}(a,b,\lambda_0)=-g(a,b)=0 $$
よって、定理が示せました。
$$ f(x,y)=x^2+y^2, \quad g(x,y)=x+y-2 $$
としてとき、 \( f(x,y) \) が条件 \( g(x,y)=0 \) をみたしながら動くときの極値を求める。
まずはじめに、
$$ g_x(x,y)=1\not=0, \quad g_y(a,b)=1\not=0 $$
が確認できた。よって、
$$ F(x,y,\lambda)=f(x,y)-\lambda g(x,y)=x^2+y^2-\lambda(x+y-2) $$
とおくと、
$$ F_x=2x-\lambda, \quad F_y=2y-\lambda, \quad F_{\lambda}=-x-y+2 $$
点 \( (a,b) \) で極値をもつとすると、ラグランジュの未定乗数法より次をみたさなければならない。
定数 \( \lambda_0 \) が存在して、
$$ F_x(a,b,\lambda_0)=2a-\lambda_0=0, \quad F_y(a,b,\lambda_0)=2b-\lambda_0=0, $$
$$ F_{\lambda}(a,b,\lambda_0)=-a-b+2=0 $$
この連立方程式を解く。第1式と第2式より、
$$ a=b=\frac{\lambda_0}{2} $$
よって、第3式より、
$$ a=b=1, \quad \lambda_0=2 $$
したがって、極値の候補となるのは
$$ (a,b)=(1,1) $$
の1点のみとなる。これが極値になることを示す。そのために、
$$ x^2+y^2=k^2, \quad x+y-2=0 $$
の第2式を第1式に代入すると、
$$ k^2=x^2+y^2=x^2+(-x+2)^2=2x^2-4x+4=2(x-1)^2+2≧2 $$
よって、 \( (x,y)\to (1,1) \) とすると、 \( k^2 \) は小さくなりながら \( 2 \) に近づく。
したがって、点 \( (1,1) \) のとき極小をとり、極小値 \( 2 \)
今回はここまでです。お疲れ様でした。また次回にお会いしましょう。